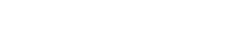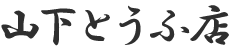といつになっても風も大雨もやってこないので不思議に思っていたら、もう通り過ぎてしまっていたらしいです。にもかかわらずあしたあさっては雨模様の様子。梅雨もまだ開けてないし、むつかしいちょっと先の天気予報のようです。
Youtubeでアドさんの鳥取の大山近辺の山登りを楽しみました。奥大山という山域名があるのでしょうか、甲が山、矢筈が山とかあの辺は「・・・せん」というふうにお山のことをいうんですね。東北で「・・・もり(森)」なんていうのと比較できますね。ゴジラの背、なんて岩稜帯が出てきてスリルがありましたが、低いながらも変化を楽しめるお山でした。今は鳥取の市街地等ではたいして雪は降らないと思うのですが(一度冬季に倉吉に行ったことがあります、べちゃべちゃ雪でした)、低い山でも上のほうは大きな木はないし斜面での生え方も十分な根曲がり具合を示していて雪の多さを感じました。
K夫妻が手蒔きで蒔いた借金ナシが発芽し始めました。カラスの来襲がないことを願うばかりです。
民放テレビで桧原村を訪れる番組がありました。その中でこんにゃく屋(製造)さんが出てきて「バタ練り」というこね方について語っていましたが、まったく同じというわけではありませんが手作業一発寄せの古典的とうふ凝固と似ているなと思いました。全体が均質で滑らかな触感になるのが豆腐もこんにゃくもライン生産の方法論になりますが、手寄せの豆腐は「豆乳を寄せていく(凝固させていく)」作業が一瞬またはそれとは正反対に静かに超ロングといった現代技術の粋を結集させたものとは対極にあります。昔は寄せる時間的ずれを目視で寄り具合を追跡しながら凝固させていく繊細な技しかありませんでしたが、現代は充填法、電子凝固、ホモゲナイズ法、乳化剤コーティングにがりの高速攪拌等といったさまざまな技術的進化を達成したおかげでだれにでも資金さえあれば簡単ににがりとうふができる時代になってしまいましたが、手作りの行き場がなくなってしまったと考える向きもあるかもしれません。
こんな時に、きょうのこんにゃくのバタ練り法にはなにか親近感を覚えてしまいました。さまざまなおおきさのつるつるの凝固体がゆるく結びついている、つまり均質なものの不均質集合体こそ古典的な「寄せの追跡法」による豆腐作りの価値・真骨頂なのです。大豆の品種差による味の違いはだいたいだれがやっても”適正な煮方でさえあれば”同じですが、寄せ方はさまざまです。全均質の豆腐は要するにライン生産可能な豆腐であり、こんにゃくのバタ練りを類推できる豆腐の手寄せは全均質でないところに意味があります。短時間内の時間差なしは不可能です。手寄のおもしろさは”豆乳の凝固結合の”おもしろさ、つまり結合したものが大雑把にばらけそれが再結合するところにあるのです。手寄せの真骨頂は結合の裏の姿/ばらけ・分解にあるのです。湯豆腐にしてもその良さが顕著です。